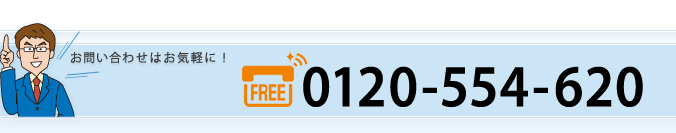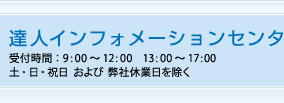事業承継税制とは?要件やメリット・デメリットを解説

企業の支配権である自社株式を贈与、相続によって承継したい場合、贈与税や相続税の負担が課題になります。このような税負担を軽減するために、事業承継税制と呼ばれる制度が設けられています。どのような場合に事業承継税制を利用できて、どのように税負担が軽減されるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、事業承継税制の内容や適用を受けるための要件、事業承継税制を利用するメリット・デメリットについて解説しています。
目次
事業承継税制とは、自社株式の贈与、相続で納税猶予や免除を受けられる制度
事業承継税制とは、事業承継のために後継者が取得した自社株式にかかる贈与税、相続税について、納税猶予や免除を受けられる制度のことです。事業承継税制の適用を受ければ、一定の要件を満たした場合に相続税や贈与税の納税が猶予され、さらに別途要件を満たすことで猶予されていた税負担が免除されます。
例えば、相続財産の大部分が自社株式で、税負担をカバーできるだけの現金を相続や贈与で後継者が受け取っていない場合、納税ができない事態にも陥りかねません。特に、自社株式の価値が高額になっている優良企業ほど後継者に多大な税負担が生じやすいことから、この問題を解決するために、事業承継税制が創設されました。
事業承継税制には一般措置と特例措置があり、それぞれ対象となる株式の範囲などが下記のように異なります。特例措置は一般措置と比べて有利な面が多い一方で、期間限定の制度です。特例措置の適用を受けるには特例承継計画を都道府県に提出する必要があります。提出期限は2026年3月31日です。
■一般措置と特例措置の主な違い
| 相違点 | 一般措置 | 特例措置 |
|---|---|---|
| 対象株式 | 発行済議決権株式総数の3分の2まで | 全株式 |
| 特例承継計画の提出 | 不要 | 必要(2026年3月31日まで) |
| 納税猶予の割合 | 贈与税:100% 相続税:80% |
贈与税:100% 相続税:100% |
| 対象となる後継者 | 筆頭株主の後継経営者1人のみ | 持ち株10%以上の後継経営者3人まで |
| 雇用確保要件 | 承継後、5年平均で相続・贈与時の80%以上の雇用維持が必要 | 承継後、80%以上の雇用維持ができなかった場合でも、理由を都道府県に報告すれば納税猶予が継続 |
| 適用期限 | なし | 2027年12月31日までの贈与、相続が必要 |
事業承継税制を理解するために、事業承継、贈与税、相続税に関する基礎的な知識を確認しておきましょう。
事業承継とは、後継者に事業を引き継ぐこと
事業承継とは、後継者に事業を引き継ぐことです。企業の場合、自社株式を贈与や相続などによって現経営者から後継者へ移転する必要がありますが、その際に相続税や贈与税がかかります。この納税が後継者の負担となり、円滑な事業承継を妨げる原因となっているケースも少なくありません。
贈与税とは、財産を贈与された方が納める税金
贈与税とは、個人間で財産の贈与が行われた場合に、財産を受け取った方(受贈者)が納める税金のことを指します。暦年課税と呼ばれる原則的な課税方法での贈与税の計算方法と税率は、それぞれ下記のとおりです。
<贈与税の計算式>
贈与税額=(受け取った財産の価額-基礎控除110万円)×贈与税率-控除額
■贈与税の税率
| 基礎控除後の財産の合計額 | 贈与税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
- ※ 成年した後継者が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与された場合
- ※ 国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
相続税とは、被相続人から財産を相続した方が納める税金
相続税とは、亡くなった方(被相続人)から財産を引き継いだ際に、財産を受け取った方(相続人)が納める税金のことを指します。相続税を計算する際は、財産の相続が可能な者として民法で定められた法定相続人の人数と、民法が定める相続割合である法定相続分などをもとに、法定相続人ごとの税額を算出して合計します。法定相続人ごとの算出税額の計算方法と税率は、それぞれ下記のとおりです。
<法定相続人ごとの算出税額の計算式>
法定相続人ごとの算出税額=課税遺産総額※×法定相続分の割合×税率
- ※ 課税遺産総額=相続財産の総額-非課税財産の価額-債務-葬儀費用+相続開始前3年以内に相続人が被相続人から贈与を受けた金額-(基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数)
■相続税の税率
| 法定相続分に応じた財産の取得金額 | 相続税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
- ※ 国税庁「No.4155 相続税の税率」
事業承継税制の適用を受けるための要件
事業承継税制の適用を受けるためには、さまざまな要件があります。企業、受贈者、先代経営者、納税猶予後の後継者や企業の状況についてそれぞれ要件があるため、一般措置と特例措置に共通する要点を中心に解説します。
承継対象となる株式を発行している企業の要件
事業承継税制には、承継対象となる株式を発行している企業に関する要件があります。贈与や相続の対象となる株式を発行する企業は、下記の要件をすべて満たしていることが必要です。
<承継対象となる株式を発行している企業の要件>
- ・ 上場企業ではないこと
- ・ 中小企業者であること
- ・ 風俗営業会社ではないこと
- ・ 資産管理会社ではないこと(一定の要件を満たす場合を除く)
後継者の要件
後継者である受贈者や相続人については、下記の要件をすべて満たしている必要があります。
<後継者の要件>
- ・ 贈与の時点、または相続開始日から5ヵ月経過した日の時点で、会社の代表権を有していること
- ・ 贈与の場合、贈与時に18歳以上であること
- ・ 贈与の場合、贈与時まで引き続き3年以上にわたって会社の役員であること
- ・ 相続の場合、相続開始の直前において役員であること
- ・ 贈与の時点、または相続開始時に、後継者および親族などの後継者と特別の関係がある者で、総議決権数の50%超の議決権数を保有していること
- ・ 取得した株式を継続して保有していること
なお、特例措置に関しては、後継者は下記の要件もすべて満たしている必要があります。
<特例措置に関する後継者の要件>
- ・ 対象となる株式について、一般措置の適用を受けていないこと
- ・ 特例承継計画に記載された後継者であること
- ・ 後継者が1人の場合、親族などの後継者と特別の関係がある者(ほかの後継者を除く)の中で最も多くの議決権数を保有すること
- ・ 後継者が2~3人の場合、総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、かつ親族などの後継者と特別の関係がある者(ほかの後継者を除く)の中で最も多くの議決権数を保有すること
先代経営者の要件
事業承継税制では、自社株式の贈与者である先代経営者に関する要件もあります。先代経営者は、下記の要件をすべて満たしていなければなりません。
<先代経営者の要件>
- ・ 会社の代表権を有していたこと
- ・ 贈与または相続開始の直前において、贈与者および親族などの贈与者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
- ・ 贈与の場合、その時点で、会社の代表権を有していないこと
なお、特例措置を適用する場合、先代経営者は下記の要件もすべて満たしている必要があります。
<特例措置に関する先代経営者の要件>
- ・ 事業承継税制に関する贈与をしていないこと
- ・ 特例承継計画に記載された先代経営者であること
- ・ 贈与の場合で、後継者が1人なら、後継者の議決権数が総議決権数の3分の2以上となるように贈与すること(後継者と先代経営者の保有議決権数の合計が3分の2に満たない場合は、すべてを贈与する必要がある)
- ・ 贈与の場合で、後継者が2~3人なら、贈与後にそれぞれの後継者の議決権数が10%以上となり、かつ、最後の贈与後に後継者が先代経営者よりも多くの議決権数を有するように贈与すること
納税猶予の適用を受けた後の主な要件
事業承継税制の適用を受けて納税が猶予された後も、下記の要件を満たさなければ、納税猶予は取り消されます。
<納税猶予の適用を受けた後に猶予を継続するための主な要件>
- ・ 事業承継税制の適用を受けた株式を譲渡しないこと
- ・ 事業承継税制の適用に関する贈与税や相続税の申告期日の翌日から5年間、後継者が会社の代表権を保有し続けること
- ・ 企業が資産管理会社に該当しないこと
- ・ 事業承継税制の適用に関する贈与税や相続税の申告期日の翌日から5年経過した日の時点で、平均して贈与、相続時の雇用の80%を維持していること
4点目の雇用維持要件については、特例措置の場合、この要件を満たせなくても都道府県に理由を報告すれば納税猶予は継続されます。
また、上記の要件を満たしている場合でも、納税猶予を受け続けるためには「継続届出書」に必要書類を添付した上で、税務署へ提出しなければなりません。納税猶予が取り消された場合、猶予されている贈与税や相続税の一部または全額と利子税を納付することになる点に注意が必要です。
事業承継税制を利用するメリット
事業承継税制を利用するメリットは、後継者の税負担を軽減できることです。本来であれば、自社株式の承継をすると、株価にもとづいて算出された相続税や贈与税が課税されることになります。
一方、事業承継税制を利用すれば納税義務が猶予され、後継者は多額の現金などを用意することなく事業を引き継げます。納税猶予の適用を受けた後に、後継者がさらに次の後継者に事業承継税制を利用して自社株式を贈与することなどの一定の要件を満たせば、猶予されていた納税義務の免除を受けることも可能です。後継者に承継できる自社株式以外の資産が少ないケースでも、税負担の懸念を解消できるため、事業承継が現実的な選択肢となります。
また、特例措置の場合、事業を承継する後継者を最大3人まで指定できるため、複数の後継者に事業を引き継ぐ際にトラブルになりにくい点もメリットです。1人に自社株式を集中して引き継がせる必要がないため、贈与や相続の時点で不公平感が生じにくくなります。
事業承継税制を利用するデメリット
事業承継税制を利用するデメリットとして、一定の取消事由に該当する場合に猶予された税額を納めなくてはならない点が挙げられます。対象となった自社株式の譲渡や代表者からの退任などが取消事由となるほか、下記のケースに該当する場合も納税猶予が取り消されるため、注意しましょう。
<主な納税猶予の取消事由>
- ・ 議決権に関する同族過半数要件を満たさなくなった場合
- ・ 後継者が同族内の筆頭株主でなくなった場合
- ・ 対象となった自社株式の議決権に制限を加えた場合
- ・ 総収⼊⾦額がゼロになった場合
- ・ 資本金、準備金を減少した場合
- ・ 合併により消滅した場合
- ・ 株式交換、株式移転により完全⼦会社となった場合
また、次の項目で解説するとおり、事業承継税制の特例措置については、手続きに手間もかかります。事業承継税制は、適用を受ける際にも、適用を受けた後も、さまざまな点を考慮しなければなりません。
事業承継税制の特例措置に関する手続きの流れ
事業承継税制の特例措置の適用を受けるためには、さまざまな書類を、提出期限を守りながら、異なる宛先に提出して手続きを進めなければなりません。贈与税と相続税の事業承継税制の手続きは、下記のような流れで進めます。
■贈与税・相続税の事業承継税制の流れ
| 順序 | 対応事項 | 対応時期 | 申請・届出などの提出先 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特例承継計画書の提出 | 2026年3月31日まで | 都道府県庁 |
| 2 | 贈与または相続による後継者への事業承継 | 2027年12月31日まで | |
| 3 | 事業承継税制の認定申請 | 贈与税・相続税の申告期限の2ヵ月前まで | |
| 4 | 贈与税・相続税の申告 | 贈与税・相続税の申告期限まで | 税務署 |
| 5 | 年次報告書・継続届出書の提出 | 税務申告後5年間、毎年1回ずつ | 都道府県庁・税務署 |
| 6 | 継続届出書の提出 | 税務申告後6年目以降、3年に1回 | 税務署 |
贈与税の場合
贈与税に関する手続きは、「納税猶予期間の開始まで」「納税猶予期間開始後5年間」「納税猶予期間開始から5年経過後」の大きく3段階に分かれます。それぞれ、下記のような手続きが必要です。
<納税猶予期間の開始まで>
- 1. 特例承認計画書を提出する(提出先は都道府県庁、期限は2026年3月31日)
- 2. 代表者を交代して贈与を実行する(期限は2027年12月31日)
- 3. 事業承継税制の認定申請を行う(申請先は都道府県庁、期限は贈与が発生した年の翌年1月15日)
- 4. 審査を経て認定書が交付される
- 5. 認定書の写しを添付して贈与税の申告を行い、納税猶予税額と利子税の額に見合う担保を提供すれば、納税猶予が始まる(申告先は税務署、期限は贈与が発生した年の翌年3月15日)
<納税猶予期間開始後5年間>
- ・ 年1回、年次報告書を提出する(提出先は都道府県庁、期限は毎年6月15日)
- ・ 年1回、継続届出書を提出する(提出先は税務署、期限は毎年8月15日)
<納税猶予期間開始から5年経過後>
- ・ 3年に1回、継続届出書を提出する(提出先は税務署、期限は6月15日)
なお、贈与税の納税猶予期間内に先代の経営者が死亡した場合は、猶予されていた贈与税額は免除され、納税猶予の適用を受けていた自社株式は相続財産とみなされて相続税の計算が行われます。ただし、その相続税の負担についても、相続税の事業承継税制への切り替え手続きを行えば、納税猶予を継続して、最終的に猶予税額の免除を受けることが可能です。
■贈与税の事業承継税制の仕組み

相続税の場合
相続税に関する手続きも、贈与税の場合と同様「納税猶予期間の開始まで」「納税猶予期間開始後5年間」「納税猶予期間開始から5年経過後」の3段階があります。
<納税猶予期間の開始まで>
- 1. 特例承認計画書を提出する(提出先は都道府県庁、期限は2026年3月31日まで)
- 2. 相続が発生したら自社株式が後継者に承継されるよう遺産分割する(2027年12月31日までに遺産分割しなければ、特例措置の適用は受けられない)
- 3. 事業承継税制の認定申請を行う(申請先は都道府県庁、期限は相続開始日から8ヵ月経過する日まで)
- 4. 審査を経て認定書が交付される
- 5. 認定書の写しを添付して相続税の申告を行い、納税猶予税額と利子税の額に見合う担保を提供すれば、納税猶予が始まる(申告先は税務署、期限は相続開始日から10ヵ月以内)
<納税猶予期間開始後5年間>
- ・ 年1回、年次報告書を提出する(提出先は都道府県庁、期限は相続税の申告期限の翌日から1年ごとに3ヵ月経過する日まで)
- ・ 年1回、継続届出書を提出する(提出先は税務署、期限は相続税の申告期限の翌日から1年ごとに5ヵ月経過する日まで)
<納税猶予期間開始から5年経過後>
- ・ 3年に1回、継続届出書を提出する(提出先は税務署、期限は相続税の申告期限後5年経過した日から3年ごとに3ヵ月経過する日まで)
納税猶予の開始後5年が経過してから、後継者が次の後継者へ事業承継税制を利用して自社株式を贈与した場合、相続税は免除されます。会社を清算した場合や、後継者が死亡した場合も同様です。
■相続税の事業承継税制の仕組み

事業承継税制を活用して、税負担の軽減を図ろう
事業承継税制は、自社株式の贈与や相続に伴って発生する納税義務の猶予を受けられる制度です。この制度を活用することにより、後継者が贈与税や相続税の納税による多大な負担を強いられることなく、円滑に事業承継を進められる可能性が高まります。事業承継税制には一般措置と特例措置があり、より有利なのは特例措置ですが、特例承継計画の提出が必要なことに加え、贈与や遺産分割の期限も定められている点に注意しなければなりません。
事業承継税制の活用を検討している場合は、贈与税や相続税の申告と、自社株式の評価が必要になるため、達人シリーズの「贈与税の達人」「相続税の達人」「財産評価の達人」の導入を併せて検討しておくことをおすすめします。
「贈与税の達人」は、贈与税の申告書や、贈与税に関連する申請書、届出書などの作成が可能なソフトです。一般的な贈与税の申告書のほか、事業承継税制の特例承継計画、認定申請書、事業承継税制を適用した場合の申告書などの作成も可能です。
「相続税の達人」でも、「贈与税の達人」と同様に、相続税の申告書の作成に加えて、事業承継税制の特例措置で必要となる各種申請書や届出書を作成することができます。
また、「財産評価の達人」は、個人の所有する財産の管理や、個別財産の評価明細書の作成ができるソフトです。贈与税、相続税の計算時に必要となる自社株式の評価も、株式の所有状況と会社規模の判定要素に関する必要最低限の入力だけで評価方式を自動判定し、簡単に正確な評価額を算出できます。
事業承継をスムーズに進めたい経営者の方は、ぜひ達人シリーズの各種ソフトをご活用ください。
監修者
石割由紀人(石割公認会計士事務所)
公認会計士・税理士、資本政策コンサルタント。PwC監査法人・税理士法人にて監査、株式上場支援、税務業務に従事し、外資系通信スタートアップのCFOや、大手ベンチャーキャピタル、上場会社役員などを経て、スタートアップ支援に特化した「Gemstone税理士法人」を設立し、運営している。
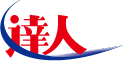


 0120-554-620
0120-554-620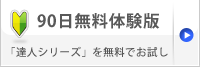
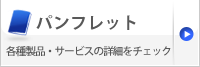
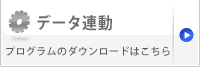
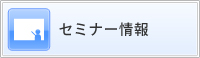
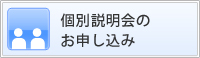
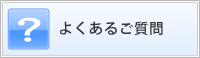
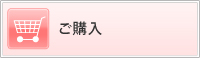
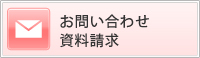



 セミナー情報
セミナー情報 個別説明会のお申し込み
個別説明会のお申し込み よくあるご質問
よくあるご質問 ご購入
ご購入