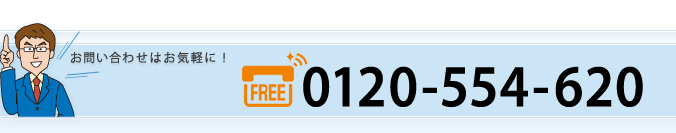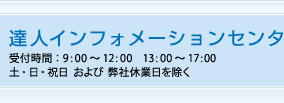支払調書とは?源泉徴収票との違いや書き方、提出期限を解説

支払調書は、報酬などの支払者が作成する法定調書の一種で、さまざまな種類があります。法定調書が作成されないケースもあるため、どのような場合に提出が必要になるのかなどがわかりにくいと感じている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、支払調書の提出義務や提出先、提出期限、提出方法のほか、源泉徴収票との違い、主な支払調書の種類、作成方法などについて解説します。
目次
支払調書とは、報酬などを支払った場合に支払先や支払金額などを税務署に報告する法定調書
支払調書とは、法人や個人に報酬などを支払った場合に支払先や年間の支払金額、報酬の内容などを税務署に報告するための法定調書のことです。法定調書は63種類あり、支払調書はこの中に含まれています。
税務署は、報酬などの支払者から提出された支払調書と、報酬の支払先から提出された所得税の確定申告書を突き合わせることにより、確定申告が正確に行われているか確認します。
■税務署による支払調書と確定申告書の突き合わせのイメージ

また、支払調書は源泉徴収が適切に行われているかを確認するためにも必要です。そのため、支払調書に源泉徴収税額を記載する欄がある場合には、正確な金額を記載しなければなりません。
支払調書の提出義務の範囲や、提出する場合の提出先、提出期限、提出方法は、下記のとおりです。
提出義務の範囲
企業などが法人や個人に報酬・料金などを支払ったからといって、あらゆるケースで支払調書の提出義務が生じるわけではありません。支払調書の提出が必要とされる範囲は、所得税法や租税特別措置法などの法令で規定されています。
提出の要否が分かれる基準は、主に報酬の種類と金額です。例えば、代表的な支払調書の1つである「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」に関しては、下記のような条件に該当した場合に提出義務が生じます。それぞれの報酬の合計額が提出義務の範囲を下回っている場合は、支払調書を提出する必要はありません。
■支払調書の提出義務が生じる報酬の種類と金額の例
| 報酬の種類 | 提出義務が生じる金額 |
|---|---|
| 弁護士、税理士、作家、画家などに支払った報酬(原稿料・講演料などを含む) | 同一人に対する支払いが5万円を超える場合 |
| 外交員、集金人、ホステスなどに支払った報酬 | 同一人に対する支払いが50万円を超える場合 |
| 広告宣伝のための賞金 | 同一人に対する支払いが50万円を超える場合 |
提出先と提出期限
支払調書の提出先は税務署で、提出期限は支払調書の種類ごとに定められています。「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」や「不動産の使用料等の支払調書」といった主要な支払調書の提出期限については、1月1日から12月31日までの1年間に同一人物に対して支払った金額の合計を、翌年1月31日までに取りまとめて提出します。支払調書の目的は、「誰がどれだけの報酬や料金を受け取っているのか」「正しく源泉徴収がなされているか」といった点を税務署が確認することです。
源泉徴収を行うべき取引において源泉徴収がなされていない場合、源泉徴収義務を負う支払者に対して罰則が科されます。したがって、支払調書の提出義務がある場合は、必ず期限までに正確な内容を記載した支払調書を提出しなければなりません。
提出方法
支払調書の提出方法には下記の4種類があります。
<支払調書の提出方法>
- ・ 書面
- ・ e-Tax
- ・ 光ディスク(CD、DVD)
- ・ 国税庁長官の認定を受けたクラウドサービス
ただし、前々年に支払調書を含めた法定調書の提出枚数が100枚以上だった場合は、書面での提出は認められません。このようなケースでは、e-Tax、光ディスク、クラウドサービスのいずれかの方法によって提出することが義務づけられています。
また、2027年1月1日以降、この基準が30枚以上となる点にも注意しなければなりません。今後、書面以外で支払調書を提出する必要に迫られる事業者の増加も想定されるため、できるだけ早期にe-Taxや光ディスク、クラウドサービスを利用した提出方法へと移行しておくことをおすすめします。
支払調書と源泉徴収票の違い
支払調書と混同されやすい法定調書として、給与所得や退職所得の源泉徴収票が挙げられます。両者の違いは支払先で、支払調書は従業員以外の支払先に報酬を支払った場合に発行しますが、源泉徴収票は企業が従業員に給与などを支払った場合に発行する法定調書です。
いずれも源泉徴収に関する法定調書ではあるものの、支払先が自社の従業員か否かによって作成すべき法定調書が異なる点に、注意しなければなりません。
主な支払調書の種類
支払調書にはさまざまな種類があります。全部で63種類ある法定調書の中で、支払調書という単語が名称に含まれているのは35種類です。このうち、代表的な支払調書として挙げられるのは、下記の4種類です。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」とは、弁護士や税理士などの専門家に報酬を支払った場合や、作家などに原稿料、講演料を支払った場合に作成する法定調書です。
■報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の書式見本

主な記載項目は下記のとおりです。詳細は、後述の「支払調書の作成方法」の項目で解説します。
<報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の主な記載項目>
- ・ 支払いを受ける者の住所・氏名
- ・ 報酬の区分(原稿料、講演料など)
- ・ 報酬の細目
- ・ 支払金額
- ・ 源泉徴収税額
- ・ 支払者の住所・氏名
作成や提出が必要になる金額の基準は報酬の支払先によって異なり、支払先が専門家やフリーランスであれば年間5万円超、外交員や集金人であれば年間50万円超となるなど、基準が変わる点に注意する必要があります。
また、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、源泉徴収義務のある個人に対する支払いだけが作成義務の対象になるわけではありません。法人に対して支払った報酬、料金で、源泉徴収の対象にならない支払いや、源泉徴収の限度額を下回っていたため源泉徴収が行われていない支払いなどについても、支払調書の作成、提出が義務づけられている点に注意してください。
不動産の使用料等の支払調書
「不動産の使用料等の支払調書」とは、法人や不動産業者の個人が、使用料などを支払った際に作成する法定調書です。
■不動産の使用料等の支払調書の書式見本

- ※ 国税庁「F1-4 不動産の使用料等の支払調書(同合計表)」
使用料などの例としては、事務所の家賃や権利金、更新料、礼金などが挙げられます。主な記載項目は下記のとおりです。
<不動産の使用料等の支払調書の主な記載項目>
- ・ 支払いを受ける者の住所・氏名
- ・ 支払いの区分(地代、家賃、船舶の使用料など)
- ・ 所在地
- ・ 細目
- ・ 計算方法
- ・ 支払金額
- ・ 斡旋者がいた場合は斡旋者の住所・氏名・斡旋手数料
- ・ 支払者の住所・氏名
「不動産の使用料等の支払調書」は、不動産や不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借り受けの対価として、同一人に対して年間15万円超の使用料などを支払った場合に作成、提出が必要になります。
ただし、支払先が法人であれば家賃や賃貸料は対象になりません。権利料や更新料などに関してのみ、支払調書の作成、提出が必要となります。
将来的に返還されることが前提となっている敷金や保証金などについても、支払調書の提出義務はないものの、返還されないことが確定した際に提出義務が生じる点に注意が必要です。また、個人の不動産事業者が賃貸借の仲介のみ行っている場合や、賃貸借の代理事業を営んでいるような場合は、支払調書の提出義務はありません。
不動産の譲受けの対価の支払調書
「不動産の譲受けの対価の支払調書」とは、法人や不動産業者の個人が不動産などを譲り受けた場合に、支払った対価について作成、提出する法定調書です。
■不動産等の譲受けの対価の支払調書の書式見本

- ※ 国税庁「F1-5 不動産等の譲受けの対価の支払調書(同合計表)」
この支払調書の作成、提出が必要になるのは、不動産や不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機を譲り受けた場合で、譲り受けには不動産の売買や交換のほか、競売、現物出資、公売などによる取引も含まれます。主な記載項目は下記のとおりです。
<不動産等の譲受けの対価の支払調書の主な記載項目>
- ・ 支払いを受ける者の住所・氏名
- ・ 物件の種類
- ・ 所在地
- ・ 細目
- ・ 数量
- ・ 取得年月日
- ・ 支払金額
- ・ 斡旋者がいた場合は斡旋者の住所・氏名・斡旋手数料
- ・ 支払者の住所・氏名
「不動産の譲受けの対価の支払調書」は、同一人に対する年間の支払総額が100万円を超える場合に、作成、提出しなければなりません。なお、個人の不動産業者に関しては、建物の賃貸借の仲介や代理が主な事業内容であれば、支払調書の提出義務は生じません。
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」とは、法人や不動産業者の個人が、不動産などの売買や貸し付けに伴う斡旋手数料を支払った場合に作成、提出する法定調書です。
■不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書の書式見本

主な記載項目は下記のとおりです。
<不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書の主な記載項目>
- ・ 斡旋手数料の支払いを受ける者の住所・氏名
- ・ 斡旋手数料が発生した契約などの区分(譲渡、譲り受け、貸し付け、借り受けなど)
- ・ 支払確定年月日
- ・ 支払金額
- ・ 斡旋にかかる不動産などの物件の種類
- ・ 物件の所在地
- ・ 物件の数量
- ・ 取引金額
- ・ 支払者の住所・氏名
「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、不動産や不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買または貸し付けの斡旋手数料として、同一人に年間15万円を超える金額を支払う場合に作成、提出します。
なお、「不動産の使用料等の支払調書」「不動産等の譲受けの対価の支払調書」のうち、「あっせんをした者」欄に必要事項が記載されていれば、「不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出は不要です。同様に、個人が不動産事業を営んでおり、事業内容が主に建物の賃貸借の仲介や代理であれば、提出義務は生じません。
支払調書の作成方法
支払調書の作成方法の詳細について、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を例に解説します。記載すべき項目は、下記の7点です。
「支払を受ける者」欄
「支払を受ける者」欄は、報酬や料金の支払いを受けた人の情報を記載する欄です。作成者から見た場合、報酬の支払先にあたります。
この欄に記載すべき事項は、支払いを受ける者の住所または所在地、氏名または法人名、マイナンバー(個人番号)または法人番号です。個人事業主で屋号がある場合、屋号のみの記載は認められません。個人の氏名を記載する必要があります。
マイナンバーや法人番号は右詰めで記載します。ただし、マイナンバーは税務署に提出する場合にのみ記載が必要です。支払いを受ける人に対して、確認用の控えとして発行するような場合には、マイナンバーを記載した状態では発行できません。
「区分」欄
「区分」欄は、報酬や料金の名称を記載する欄です。例えば、原稿料や印税、講演料、弁護士報酬、税理士報酬、診療報酬といった文言を記載します。
印税の場合は初版について支払われた印税と、それ以外の事由で支払われた印税は区別して記載しなければなりません。初版の場合は「書き下ろし初版印税」と、そのほかの場合は「その他の印税」と明記します。
「細目」欄
「細目」欄は、区分よりもさらに詳細な報酬・料金の内容を記載する欄です。例えば、原稿料であれば支払回数、印税であれば対象となる書籍や作品の名称、弁護士報酬であれば関与した事件名といったように、報酬・料金の詳細を記載する必要があります。
「支払金額」欄
「支払金額」欄は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った金額を記載する欄です。ここに記載すべき金額には、未払いであっても12月31にまでの支払いが確定している報酬や、源泉徴収の対象外となる報酬も含まれます。未払い分の金額については、各欄の上段に内書きする点に注意が必要です。
なお、記載する金額や提出義務の判断基準となる金額は、原則として消費税も含めた税込金額です。ただし、請求書などで消費税額が明確に区分されている場合には、消費税を含めない金額でも差し支えありません。
「源泉徴収税額」欄
「源泉徴収税額」欄は、源泉徴収するべき年間の所得税・復興特別所得税の合計額を記載する欄です。未払いの報酬・料金に関する源泉徴収税額については、記入欄の上段に内書きします。
なお、災害による被害に遭った方など、源泉所得税の徴収が猶予されている場合には猶予分の税額は含まれません。その場合、猶予分を差し引いた源泉徴収税額を記載します。
「摘要」欄
「摘要」欄は、特筆すべき事柄がある場合に記載する欄です。下記のケースに該当する場合に、所定の内容を記載します。
■「摘要」欄に記載が必要なケースと記載内容
| 記載が必要になるケース | 記載内容 |
|---|---|
| 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬に関する支払調書を作成するケースで、診療報酬の中に家族診療分がある場合 | 家族診療分の金額を記載し、金額の冒頭に「家族」と四角囲みで記載 |
| 災害により被害を受けたため、源泉所得税および復興特別所得税の徴収が猶予されている場合 | 猶予されている税額を記載し、金額の冒頭に「災」と丸囲みで記載 |
| 広告宣伝のための賞金が金銭以外の場合 | 賞金の種類などの明細を記載 |
| 源泉徴収の免除証明書を提出済みの場合や、そのほかに法律上源泉徴収の必要がない場合 | その旨を記載 |
「支払者」欄
「支払者」欄は、報酬や料金を支払った法人や個人の情報を記載する欄です。報酬などを支払った方から見た場合、自身の情報にあたります。
記載すべき事項は、支払者の氏名または名称、住所または所在地、電話番号、マイナンバーまたは法人番号です。ただし、支払いを受ける人に対して確認用の控えとして発行するような場合には、マイナンバーを記載した状態では発行できない点に注意してください。
支払調書を作成する際のマイナンバーの取得と管理
税務署に提出する支払調書には、原則としてマイナンバーを記載することが義務づけられています。したがって、作成者は支払先から事前にマイナンバーの提供を受け、本人確認を行うなど、適切な方法で取得しなければなりません。さらに、取得したマイナンバーについては、適切な管理も必要です。
マイナンバーは個人情報に該当するため、取得した情報が漏洩したり、紛失したりすることのないよう細心の注意を払う必要があります。セキュリティ対策が講じられた専用のシステムを利用するなど、具体的なリスク管理の手段を検討しましょう。
なお、報酬の支払先に対して支払調書の写しを交付する際には、マイナンバーを記載した状態で送付できないため、税務署へ提出する支払調書と支払先へ送付する支払調書は分けて作成する必要があります。
支払調書の提出義務と提出期限を遵守しよう
支払調書は法人や個人に報酬・料金などを支払った場合に、その事実を税務署へ報告するための法定調書です。報酬の種類ごとに合計35種類の支払調書が存在するため、支払った報酬に応じて提出する支払調書を適切に選択する必要があります。また、支払調書の提出義務が生じる金額に関しても、報酬の種類によって異なる点に注意しなければなりません。
支払調書の提出義務がある場合は、必ず提出期限を守りましょう。期限を遵守しつつ正確な内容の支払調書を提出するためにも、法定調書の作成に対応したソフトを活用することをおすすめします。その場合、達人シリーズの「年調・法定調書の達人」「電子申告の達人」「外部連携」の活用がおすすめです。
「年調・法定調書の達人」では、法人や個人の年末調整、法定調書の作成に対応していて、インポート機能により入力時間を削減するとともに、手動による入力ミスも回避できます。支払調書をe-Taxで提出したい場合には、電子申告のデータ作成から送信、受信確認までの一連の作業を簡単な作業のみで完結できる「電子申告の達人」が最適です。さらに「電子申告の達人」のカスタマイズオプションである「外部連携」を活用すると、外部システムで作成したデータを電子申告データに変換できます。
法定調書を多数発行する必要がある場合や、作成にかかる時間と労力をできるだけ削減したい場合は、「達人シリーズ」をご検討ください。
監修者
石割由紀人(石割公認会計士事務所)
公認会計士・税理士、資本政策コンサルタント。PwC監査法人・税理士法人にて監査、株式上場支援、税務業務に従事し、外資系通信スタートアップのCFOや、大手ベンチャーキャピタル、上場会社役員などを経て、スタートアップ支援に特化した「Gemstone税理士法人」を設立し、運営している。
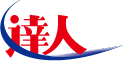


 0120-554-620
0120-554-620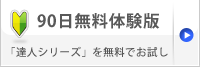
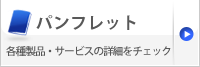
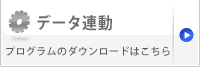
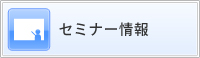
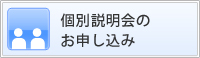
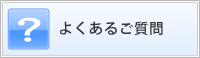
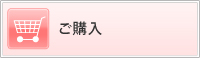
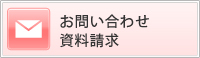



 セミナー情報
セミナー情報 個別説明会のお申し込み
個別説明会のお申し込み よくあるご質問
よくあるご質問 ご購入
ご購入