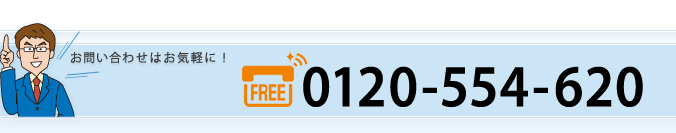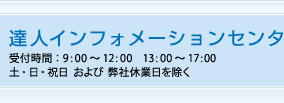経営分析ツールとは? 導入するメリットや機能を解説

企業の経営戦略を立案したい場合は、経営判断に役立つ各種データを分析できる経営分析ツールを活用すると便利です。経営分析ツールを活用することで、企業における業績指標や財務状況などをより客観的かつリアルタイムで把握しやすくなります。企業の業績改善につなげるために、経営分析ツールの導入を検討している方も、少なくないのではないでしょうか。
ここでは、経営分析ツールを導入するメリットや主な機能、選定のポイントのほか、導入時の注意点を解説します。
目次
経営分析ツールとは、企業の財務状況や業績指標などを分析して意思決定をサポートするツール
経営分析ツールとは、企業の財務状況や業績指標に対する達成度合いなどを分析し、意思決定をサポートするツールのことです。経営判断に必要とされるさまざまなデータを集約・統合し、視覚的にわかりやすく表示する機能を備えています。
従来、経営分析を行うには財務諸表を参照したり、さまざまな資料を収集したりしてデータを集め、分析レポートを作成する必要がありました。分析に必要なデータが複数の部門にまたがっているケースも珍しくないことから、従来の方法で抜け漏れなくデータを収集し、正確に分析するためには、相応の時間と労力が必要となります。こうした一連のデータ収集・分析の工程を効率化するための仕組みが、経営分析ツールです。
経営分析ツールの主な機能
経営分析ツールには、ツールごとにさまざまな機能が備わっています。基本的にどのツールにも共通している機能としては、下記の2点が挙げられます。
実績管理・分析機能
経営分析ツールは、重要業績評価指標(KPI)などの意思決定に資するさまざまな数値の実績データを管理し、分析する機能を備えているのが一般的です。例えば、設定したKPIに対する達成度や上昇・下落率などを分析し、レポートとして表示するといった機能です。KPIに関する分析のために膨大な種類・量のデータを必要とするケースは少なくありません。こうしたデータ収集と分析の工程をツールで自動化することにより、ユーザーは本来の目的である経営判断に集中しやすくなります。
また、分析結果は保存・蓄積されていくため、経時的な変化や過去の傾向を参考にすることで、より的確な経営判断ができるようになります。
経営予測機能
一般的な経営分析ツールには、将来の経営予測に役立つ機能も備わっています。過去に得られたデータの傾向とその分析結果を通じて、現状を踏まえた今後の実績推移や予測値をシミュレーションできる機能です。シミュレーション結果をもとに改善策を見いだしたり、先手を打って改善策を講じたりする上で役立ちます。
経営予測では過去の経験則が役立つ場合もありますが、経験則だけで将来を予測すると、先入観にとらわれて判断を誤るリスクも潜んでいます。データにもとづいたシミュレーション結果を参照することで、より客観的な判断が可能です。
経営分析ツールを導入するメリット
経営分析ツールの活用により、企業が自社の経営を分析する場合だけでなく、税理士による顧問先の経営支援も容易になります。税負担も考慮しつつ経営支援に携われることは、税理士だからこそ実現できる強みです。経営分析ツールの導入を通じて、企業・税理士の双方が得られる主なメリットは、下記のとおりです。
企業のデータを一括で収集して分析できる
企業内に散在するデータを集約した上で、それらを踏まえた分析が可能になることは、経営分析ツールを導入するメリットのひとつです。経営分析に必要なデータや資料が、複数部門にまたがっていることは珍しいことではありません。人の手でこれらのデータや資料を収集し、取りまとめて分析するには多大な労力と時間を要します。
経営分析ツールを活用することで、一連のデータ収集と分析を一括で実行できます。異なるファイル形式や体裁でまとめられているデータを、人の手で抽出して取りまとめる必要はありません。刻々と更新されていく各種データをリアルタイムで収集し、最新データにもとづく分析結果を即座に得ることも可能です。
分析結果を視覚的に把握できる
収集したデータをグラフや表などの形式に自動で加工し、視覚的に把握しやすい状態で表示できる点も、経営分析ツールのメリットです。分析結果を直感的に理解できるため、意思決定に必要な情報を素早く確認できます。
現状の財務状況や業績指標の達成度合いが視覚的に示されていることは、意思決定の根拠や背景を説明する際にも役立ちます。経営会議の場で提示する資料に数値が羅列されているだけでは、資料で伝えたいポイントが正確に伝わらないかもしれません。経営陣がより適切な判断を下せるよう、視認性の高い資料を作成する必要がある場合にも、経営分析ツールのレポート機能が効果を発揮します。
■経営分析ツールのメリットのイメージ

データ集計のミスが発生しなくなる
経営分析ツールのメリットは、データ集計を行う際のヒューマンエラーを回避できる点です。Excelなどに手動で入力されたデータをもとに経営分析を進めた場合、数値や数式、集計項目の範囲指定の誤りなどが発生している可能性があります。それだけでなく、データの入力に時間がかかり、最新の分析結果が得られないケースも少なくありません。
経営分析ツールを導入することで、分析に必要なデータを自動で収集できるようになります。集計から分析までの工程も含めて自動化されるため、人の介在によるミスの発生リスクを防ぐことが可能です。
経営分析ツール選定のポイント
経営分析ツールと一口にいっても、ツールごとに機能や特徴は異なります。経営分析ツールを選定する際には、下記のポイントを意識して選びましょう。
必要な機能が搭載されているか
想定している使用方法に必要な機能が搭載されているかどうかは、必ずチェックしておきたいポイントです。予実管理や財務診断、KPI管理、取引分析など、備わっている機能はツールごとに異なります。活用したい機能が搭載されていないツールを導入してしまうと、手動による集計・分析の工程が残ることになりかねません。
どのような機能が必要かを適切に判断するためには、経営分析ツールを導入する目的を明確にしておくことが重要です。現状の意思決定のプロセスや分析方法が抱えている課題を洗い出し、ツールによって解決すべき課題を確認しなければなりません。導入目的を明確化することは、不要な機能が多数搭載されたツールを選定してしまうリスクを回避することにもつながります。
すでに使用しているソフトと連携できるか
経営分析ツールを選定する際には、現状で活用しているソフトウェアとの連携性についても確認しておく必要があります。経営分析ツールのメリットのひとつは、データの自動収集ができる点です。経営分析に必要なデータをさまざまなソフトから収集して統合することで、意思決定に資する分析結果を得られます。連携できないソフトがある場合、手動による集計・分析をツール導入後も継続しなければなりません。
連携可能なソフトの種類は、経営分析ツールごとにさまざまです。データ収集元となるソフトをリストアップし、連携が可能なツールかどうかを比較検討しましょう。また、対応しているソフトだけでなく、インポートが可能なファイル形式についても確認しておくことをおすすめします。
出力されるレポートがわかりやすいか
経営分析ツールが出力するレポートのわかりやすさも、経営分析ツールを選定する際のポイントのひとつです。「意思決定に必要な情報がひと目で確認できる状態になっているか」「掲載されているデータ項目に過不足はないか」といった点を詳細に確認しておく必要があります。
こうしたツールの導入効果は、実際に活用してみないとわからない面もあるのが実情です。無料トライアルなどを活用し、実際のデータをインポートした上でレポートを出力してみることをおすすめします。ツールによっては、レポートのサンプルやデモ画面などが紹介されているケースもありますが、想定した使い方ができるか実際に確認しておくほうが確実です。
経営分析ツールの導入における注意点
経営分析ツールを導入する際には、注意しておかなければならない点もあります。代表的な注意点としては、下記の2点が挙げられます。
導入コストだけでなく運用コストも検討する
経営分析ツールを導入する際は、導入コストだけでなく運用コストも検討しましょう。経営分析ツールのコストには、大きく分けて導入コストと運用コストの2つがあります。導入時は導入コストに着目しがちですが、導入後に継続して負担することになる運用コストについても、慎重に検討しておくことが重要です。
ツールによっては、プランごとに提供されている機能や対応可能なユーザー数が異なるケースもあります。将来の増員や部門の新設などに伴ってユーザー数が増えた際、利用料が想定を超えて増大するようなことがないか、事前によく確認しておかなければなりません。
また、運用コストには人的コストも加味しておく必要があります。導入に際して社員研修や操作方法のレクチャーを実施したり、新たに人材を採用したりすることも想定されます。運用コストの負担が利益を圧迫するような事態を避けるためにも、導入コストと運用コストの両面を考慮してください。
最初から全社規模で導入しない
経営分析ツールは、全社規模のデータを収集・分析することを目的に導入するケースが少なくありませんが、導入当初から全社規模での導入にこだわる必要はありません。ツールの運用方法や効果的に活用するためのノウハウが蓄積されていない状態で大規模な導入に踏み切ってしまうと、現場が混乱するだけでなく、ツール本来の効果を実感できないおそれもあります。結果としてツールが定着せず、導入コストが無駄になってしまう可能性も否定できません。
まずは小規模な範囲で試験的に導入し、テスト運用期間を設けることをおすすめします。一定の効果が確認できた段階で徐々に規模を拡大していき、無理なく導入・運用を進めましょう。
経営分析ツールを活用して、経営判断や経営支援に役立てよう
経営分析ツールは、客観的なデータにもとづく企業の財務状況や業績の分析を通じて、適切な意思決定をサポートするツールです。企業が保有するデータを一括で収集・分析できるほか、分析結果を視覚的にわかりやすい形で表示でき、データ集計のミスを回避できるため、経営陣の経営判断や税理士などの経営支援に役立ちます。
一方で、搭載されている機能や出力されるレポートの形式はツールごとに異なるため、導入目的を明確にした上で、課題解決につながるツールを選定しましょう。
監修者
石割由紀人(石割公認会計士事務所)
公認会計士・税理士、資本政策コンサルタント。PwC監査法人・税理士法人にて監査、株式上場支援、税務業務に従事し、外資系通信スタートアップのCFOや、大手ベンチャーキャピタル、上場会社役員などを経て、スタートアップ支援に特化した「Gemstone税理士法人」を設立し、運営している。
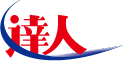


 0120-554-620
0120-554-620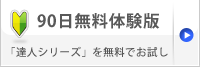
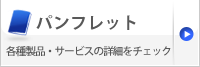
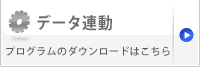
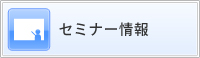
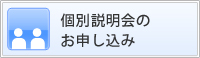
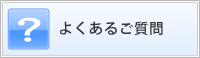
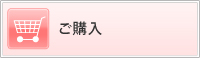
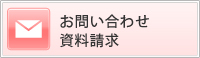



 セミナー情報
セミナー情報 個別説明会のお申し込み
個別説明会のお申し込み よくあるご質問
よくあるご質問 ご購入
ご購入