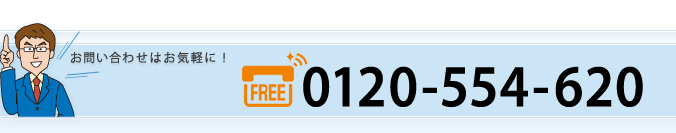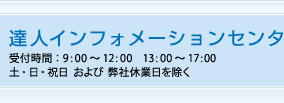確定申告の必要書類・添付書類についてケース別に解説

所得税の確定申告をする際には、必要書類や添付書類に不足がないよう準備を整えておく必要があります。必要書類は申告する内容に応じて変わるため、確定申告に向けて、必要書類について確認しておきたい方も少なくないのではないでしょうか。
ここでは、確定申告に必要な書類や、フリーランスなどの個人事業主、会社員、年金受給者がそれぞれ提出する必要のある書類について解説します。
目次
確定申告に必要な書類
確定申告では、さまざまな書類を提出する必要があります。確定申告は、1月1日から12月31日までの年間の所得金額や控除額、納めるべき所得税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日(土日祝日の場合は翌平日)までのあいだに税務署に申告する手続きです。所得金額や税額の内容を申告するための確定申告書をはじめとして、下記のような書類が必要になります。
確定申告書
確定申告書は、1年間の収入金額や所得金額、所得控除額(所得から差し引かれる金額)、課税所得に対してかかる所得税の金額などを記載するための書類です。確定申告書には下記のように第一表から第四表までの種類があり、第一表・第二表については必ず提出することになります。
■確定申告書第一表から第四表の内容
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 第一表 | 収入金額・所得金額・控除額などの計算結果を記載 |
| 第二表 | 第一表に記載した金額の詳細を記載 |
| 第三表 | 申告分離課税を申告する場合に作成して提出 |
| 第四表 | 損失申告をする場合に提出 |
なお、かつては「確定申告書A」「確定申告書B」の2種類がありましたが、2023年からはその区分は廃止されました。
本人確認書類
確定申告書を提出する際には、併せて本人確認書類を提示または写しを添付する必要があります。本人確認書類は、マイナンバーカードを持っている場合はマイナンバーカードのみで差し支えありません。マイナンバーカードを持っていない場合には、マイナンバー(個人番号)を確認するための番号確認書類と、マイナンバーの持ち主であることを確認するための身元確認書類がそれぞれ1点ずつ必要です。
番号確認書類の例としては、マイナンバー通知カードや、マイナンバーの記載がある住民票の写し・住民票記載事項証明書などが挙げられます。身元確認書類には、運転免許証や公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどが該当します。
■本人確認書類として必要になる書類のイメージ

所得金額がわかる書類
確定申告の対象となる年の所得金額がわかる書類も、事前に準備すべき書類のひとつです。具体的には、下記のうちいずれかを用意する必要があります。
<所得金額が確認できる書類の例>
- ・ 青色申告決算書(青色申告の場合)
- ・ 収支内訳書(白色申告の場合)
- ・ 給与所得の源泉徴収票
- ・ 公的年金等の源泉徴収票
青色申告決算書または収支内訳書は、確定申告書に添付して提出します。給与所得や公的年金等の源泉徴収票については添付する必要はありません。源泉徴収票はあくまでも申告書を記載する際に参照するための書類として位置づけられ、2019年4月より確定申告書への添付は不要となりました。
各種所得控除の申告に必要な書類
確定申告で所得控除について申告する場合は、原則として控除証明書などの書類の添付が必要になります。所得控除とは、納税者の状況に応じて所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。所得税は、所得控除後の金額に対して税率を掛けて計算するため、所得控除の額が大きいほど課税される所得税は少なくなります。主な所得控除の種類と、それぞれの所得控除の申告時に必要な書類は下記のとおりです。
■主な所得控除の内容と申告に必要な書類の例
| 所得控除の種類 | 内容 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 社会保険料控除 | 健康保険や国民年金、厚生年金などの社会保険料を支払った場合に、支払った金額の全額を所得から控除できる | 社会保険料控除証明書 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済や、個人型確定拠出年金(iDeCo、イデコ)の掛金を支払った場合に、支払った掛金の全額を所得から控除できる | 小規模企業共済等掛金控除証明書(iDeCoの場合は、小規模企業共済等掛金払込証明書) |
| 生命保険料控除 | 民間保険会社の生命保険や、介護保険、医療保険などの保険料を支払った場合に、支払った金額のうち一定額を所得から控除できる | 生命保険料控除証明書 |
| 地震保険料控除 | 火災保険に付帯して地震保険の保険料を支払った場合に、地震保険部分の保険料のうち一定額を所得から控除できる | 地震保険料控除証明書 |
会社員など給与所得者の方については、社会保険料控除は年末調整で適用されているため、確定申告の際にあらためて社会保険料控除証明書を添付する必要はありません。また、そのほかの書類に関しても年末調整の際に勤務先へ提示した書類がある場合は、確定申告時には提出は不要です。
なお、ふるさと納税をした場合には、「ワンストップ特例制度」を利用したかどうかによって確定申告時に所得控除を申告すべきかどうかが異なります。ワンストップ特例制度とは、給与所得者などがふるさと納税を行った際に、この制度の適用を申請することにより、確定申告をしなくても寄附金控除が適用される制度のことです。
ワンストップ特例制度を利用しなかった場合は確定申告をしなければならなくなり、確定申告書の寄附金控除欄への記入と併せて、寄附をした自治体が発行する受領書などの添付が必要です。
銀行口座がわかる書類
所得税が還付される場合、銀行口座がわかる書類も用意する必要があります。銀行口座の情報は、還付金の入金先として確定申告書に記載します。確定申告書への記載時に確認するのみで、写しなどを添付して提出する必要はありません。キャッシュカードや預金通帳など、口座情報がわかる書類を手元に用意しておくと、確定申告書の作成をスムーズに進められます。
フリーランスなどの個人事業主の場合の必要書類
フリーランスなどの個人事業主の場合、申告方法によって必要な書類が異なります。青色申告、白色申告、それぞれの場合で必要となる書類は下記のとおりです。
青色申告の場合
青色申告をする場合には、確定申告書や本人確認書類などと併せて青色申告決算書を添付しなければなりません。青色申告決算書を添付することで、税務署は所得金額の詳細な内容を把握できるようになります。
青色申告決算書の記載内容は、適用を希望する青色申告特別控除の種類によって異なります。10万円の控除を適用するのであれば、添付書類は損益計算書のみで差し支えありません。一方、55万円または65万円の控除を適用するのであれば、複式簿記による記帳と、貸借対照表と損益計算書の添付が必要です。さらに、青色申告特別控除のうち最も節税効果が高い65万円の控除を適用するには、貸借対照表と損益計算書の添付に加え、e-Taxによる確定申告書の提出か優良な電子帳簿の保存が必須となります。
なお、青色申告をした際の作成書類や添付書類には、保存期間が定められています。確定申告書、青色申告決算書などの帳簿・決算関係書類と、領収書などの現金預金取引等関係書類は7年間、そのほかの請求書や契約書などの書類は5年間保存しておかなくてはなりません。ただし、前々年分の所得が300万円以下の場合、現金預金取引等関係書類の保存期間は5年です。
青色申告は、白色申告と比べて作成すべき書類が多いため、白色申告よりも手間がかかる面があります。一方で、青色申告をすることによって、下記のようなメリットもあります。
<青色申告の主なメリット>
- ・ 青色申告特別控除(最大65万円)が適用される
- ・ 家族に支払った給与を、給与額として相当であれば全額経費として計上できる
- ・ 赤字を3年間繰り越せる
- ・ 少額減価償却資産の特例が適用される
- ・ 一括評価分の貸倒引当金を経費として計上できる
白色申告の場合
白色申告の場合、確定申告書や本人確認書類などに加えて、収支内訳書の添付が必要です。収支内訳書の記載事項は、青色申告決算書として作成する貸借対照表や損益計算書と比べて少なく、簡素な形式となっています。また、記帳に関しても単式簿記でよいことから、簿記の知識があまりない方でも比較的簡単に確定申告ができます。
注意点として、青色申告では適用される青色申告特別控除や赤字の繰り越し、少額減価償却資産の特例などのメリットが白色申告にはありません。確定申告を簡潔に終えられること以外に、白色申告を選択するメリットはほとんどないといえます。
なお、白色申告での作成書類や提出についても、保存期間が決められています。収入金額や経費を記載した法定帳簿については7年間、業務に関連する法定帳簿以外の帳簿(任意帳簿)や、棚卸表、請求書などの決算・業務に関連して作成した書類については5年間保存しておかなくてはなりません。
会社員の場合の必要書類
会社員などの給与所得者の場合、基本的に勤務先で年末調整が実施されるため、所得金額や所得税額を自分で計算する必要はありません。ただし、年末調整では申告できない所得控除があることから、下記に挙げる所得控除の適用を受けたい場合には、確定申告が必要です。
<年末調整では申告できない所得控除の例>
- ・ 医療費控除
- ・ 寄附金控除
- ・ 雑損控除
また、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合も、初年度は確定申告が必要です。年末調整を行っていた場合でも、確定申告によってこれらの控除の適用を受けることにより、課税所得金額が年末調整時よりも少なくなり、結果として納めすぎていた所得税の還付を受けられる可能性があります。各種控除証明書とともに、確定申告書や本人確認書類といった必要書類を準備し、管轄の税務署へ提出しましょう。
■各種控除を申請する際の主な必要書類
| 控除の種類 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 医療費控除 | 医療費控除の明細書 |
| 寄附金控除 |
|
| 雑損控除 | 災害や盗難、横領などの被害に関する支出の領収書 |
| 住宅ローン控除 |
|
会社員が確定申告をする際には、勤務先で発行された源泉徴収票を確認し、記載されている収入金額や所得金額を確定申告書に記入するため、源泉徴収票が必要です。源泉徴収票は一般的に12月下旬から1月ごろに発行されることから、確定申告期間まで紛失しないよう保管しておかなければなりません。万が一、源泉徴収票を紛失してしまった際には、勤務先に連絡することで再発行してもらうこともできます。
なお、所得控除や住宅ローン控除を適用したい場合以外に、給与所得者で確定申告が必要になるのは下記に該当する方です。
<会社員で確定申告が必要になる主なケース>
- ・ 複数の事業者から給与を受け取っている場合で、年末調整されなかった勤務先での給与収入と給与以外の所得金額の合計が年間20万円を超えている
- ・ 給与以外の所得金額が年間20万円を超えている
- ・ 年の途中で退職し、年末調整を受けていない
- ・ 給与収入が年間2,000万円を超えている
年金受給者の場合の必要書類
年金受給者は、場合によっては確定申告が必要となり、状況に応じて異なる添付書類を提出しなければなりません。年金受給者の場合、下記の条件に該当すると、確定申告が必要です。
<年金受給者で確定申告が必要なケース>
- ・ 公的年金の受取額が400万円を超えている
- ・ 公的年金以外の収入が年間20万円を超えている
- ・ 各種控除を申告する必要がある
公的年金以外の収入が年間20万円を超えている場合は、その所得を証明する書類を本人確認書類などとともに確定申告書に添付した上で、管轄の税務署へ申告しなくてはなりません。各種控除を申告する場合は、適用を受ける制度に応じて、控除証明書などの添付も必要となります。
また、年金受給者でも、公的年金等の源泉徴収票の内容を確定申告書に記載する必要があるため、源泉徴収票を保管しておかなければならない点は給与所得者と同様です。
添付書類の添付方法
確定申告書に各種書類を添付する際、紙で申告する場合とe-Taxで申告する場合とでは添付方法が異なります。それぞれ、下記のような方法で書類を添付してください。
紙で申告する場合
紙で申告する場合には、添付書類を添付書類台紙に貼付します。添付書類台紙は本人確認書類の写しを貼付するための台紙と、各種控除証明書などを貼付するための台紙に分かれているため、所定の台紙の「のりしろ」部分にのり付けしましょう。添付すべき書類のサイズによっては貼付が難しいようなら、テープやホチキスを使用して台紙にとめても問題ありません。
e-Taxで申告する場合
e-Taxによる電子申告をする際には、一部の添付書類は、PDF形式のイメージデータで提出することが可能です。また、社会保険料控除証明書や生命保険料控除証明書、雑損控除の証明書など、提出を省略できる書類もあります。提出を省略できない書類のうち、イメージデータによる提出が認められていない書類については、郵送や税務署窓口への持ち込みによって提出しなければなりません。
添付を省略できる書類については、e-TaxのWebページ「e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。」を確認しておくことをおすすめします。
確定申告の必要書類・添付書類を把握して、不備のない申告をしよう
確定申告では、1年間の所得金額や控除額、納めるべき所得税額などを正確に申告しなければなりません。期限を守るのはもちろん、必要書類に不備がないよう細心の注意を払って準備を進める必要があります。個人事業主だけでなく、場合によっては会社員などの給与所得者や年金受給者であっても確定申告が必要になるケースもあるため、それぞれの場合での必要書類・添付書類を十分に確認した上で、不備のないよう確定申告をしましょう。
確定申告をスムーズに進めるには、申告書作成ソフトを活用するのが得策です。所得税の申告書・決算書・内訳書をはじめ、添付書類についても作成可能な「所得税の達人」は、確定申告をできるだけ簡単に、かつ正確に行いたい方に適しています。青色申告決算書、収支報告書のどちらにも対応している上に、データの取り込み機能や連携機能が備わっているため、会計ソフトなどのデータを反映できる点も大きなメリットです。
また、消費税の確定申告も併せて行いたい場合は、「消費税の達人」で申告書や付表を簡単に作成することもできます。確定申告をスムーズに進めて、必要書類・添付書類を漏れなく提出したい方は、「所得税の達人」「消費税の達人」をぜひご活用ください。
監修者
石割由紀人(石割公認会計士事務所)
公認会計士・税理士、資本政策コンサルタント。PwC監査法人・税理士法人にて監査、株式上場支援、税務業務に従事し、外資系通信スタートアップのCFOや、大手ベンチャーキャピタル、上場会社役員などを経て、スタートアップ支援に特化した「Gemstone税理士法人」を設立し、運営している。
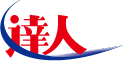


 0120-554-620
0120-554-620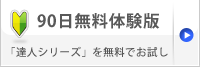
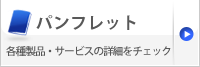
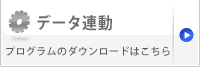
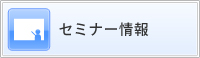
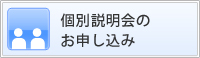
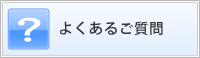
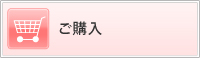
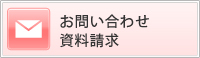




 セミナー情報
セミナー情報 個別説明会のお申し込み
個別説明会のお申し込み よくあるご質問
よくあるご質問 ご購入
ご購入